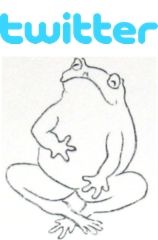今週のメルマガの前半部の紹介です。
ドワンゴの川上会長といえば、以前から熱心な終身雇用論者としても有名ですね。
なんてセリフを見ると、なんだか連合や重厚長大メーカーの役員の話を聞いてるような気分になります。
さて、そんな異色のドワンゴですが、OBのブログでしっかり「追い出し部屋」があることが明らかとなり、一部で話題となっています。
参照:ドワンゴは大量退職に関する印象操作をやめろ
しかも、総務に集めて社内の備品補充させるって相当えげつないですね。普通の大企業なら温情措置として元の部署や事業所から隔離します。まあ悪く言えば横のつながりを絶つという意味もありますが、元の同僚と顔を合わせなくてもすむようにとのささやかな気遣いも入っています。それを社内の備品補充して回らせるって、なんだか毎日、市中引き回しするようなもんですね。ようやるわと思います。
なぜ「新人をじっくり育てたい」会社が人を追い出す必要があるんでしょうか。というか、そもそも会長の言う“終身雇用”とは何なのでしょうか。いい機会なのでまとめておきましょう。
なぜトップは終身雇用を美化し、人事部は否定するのか
実は、終身雇用の方がいいと考えている経営トップは意外と多くて、ざっくり筆者の感覚で言うとだいたい3割くらいはそうですね。これは恨まれるのがイヤだとか世間体云々ではなく、本気で「終身雇用の方がいろいろ便利だし優れている」と信じている割合です。当然、川上氏もその一人でしょう。
一方、これが人事部長だと、恐らく9割以上は「もう終身雇用じゃやっていけない」と考えています。筆者の知る限り、例外は新日鉄くらいですね。それくらい、管理部門的には終身雇用は過去の遺物扱いとなっています。
なぜこのギャップは生まれるのか。理由はシンプルで、普段向き合っている人材が違うからです。経営トップになれば、当然、周囲には社内でも超優秀な人材が集います。そして、ことあるごとに、痒い所に手が届くような感じでサポートしてくれます。しかも彼らは忠誠心に富みいちいち年俸交渉なんかしなくてもずっと会社のために働いてくれます。終身雇用の枠内で勝ち取ったモノを今さら投げ打って飛び出したりなんて、普通のサラリーマンはしませんから。どんな無理難題を吹っ掛けても愛社精神の名のもと、過労死するまで頑張ってくれることでしょう。
一方、これが人事部だと付き合う人間は180度変わります。もちろん優秀者も相手しますけど、割合で言えば優秀者と真逆な人たちとのお付き合いが圧倒的になります。具体的にはこんな人たちです。
・最低限、言われたことしかやらない人
・言われたことすらやらずに、ただ席に座ってるだけのマネキン状態の人
・仕事はしないけど休み時間にマルチの勧誘する人
・仕事はしないけど休み時間に宗教(ry
・たいして仕事してないクセに残業時間だけは毎月きっちり100時間付ける人
・めんどくさい仕事がたまるとばっくれる人
・有休に加えてよくわからない理由でさらに何か月か休む人
・病気休職から復職して数か月後にまた休職しようとする人
・上司や同僚に監視されいじめられていると言い張る人
・なんでパソコン使わないんですか?と内線で尋ねると「FBIに盗聴されているからです」と手紙持ってくる人
・異動先が気に入らないという理由でサボタージュする人
・上司に注意されると暴れる人
・懲戒解雇されたのになぜか毎日会社に来て居座る人
・社外ユニオンと組んで会社から金引っ張ろうとする人
上記のようなステキな方々との終わりの無い死闘を繰り広げるのが勤労部門のメインの仕事だったりします。よく、現場知らない労働弁護士とか実質社会経験ゼロの学者あたりが「日本企業もやろうと思えば解雇は出来る」って言ってたりしますけど、あれ嘘ですから。たとえば何にもやろうとしないマネキンを解雇するなら、業務命令書を毎日作って本人に手渡して、なにもやらなかったという証拠をそれなりの期間(たとえば一年くらい)積み重ねた上で解雇したら裁判になっても多分勝てるんでしょうけど、ただでさえ本業で忙しいのにそんなめんどくさいことやってる人事の人に会ったことないですね。
というわけで人事の人間ならたいていは終身雇用という仕組みそのものに厭世的になっているものです。まとめると、組織内できわめて優秀で忠実な人材に囲まれているがゆえにトップは終身雇用を愛し、超問題児と日々顔を突き合わせている管理部門はその限界を痛感しているというわけです。
という観点からすれば、川上氏の「社員を部品みたいに使い捨てにするのは間違いだ、今の社員にはずっとうちで働いて欲しい」という意見は、飾らない本音でしょう。ただし、氏の言う“社員”なるものは、優秀でしっかり会社に貢献してくれる社員という意味であり、そうでない人は管理部門がしっかり仕事してちゃんと組織として新陳代謝させてまっせという話ですね。
そもそも、筆者は、終身雇用がちゃんと維持されている組織で、“追い出し部屋”的な要素がまったく存在しない組織はありえないと思っています。どんな組織であれ、雇用調整の要は必ず生じます。であれば、人を解雇できない以上、追い込んで自発的に辞めさせるための仕組みが必ず必要だからです。たとえば、霞が関のキャリア官僚は40歳あたりからどんどん外の組織に出されますが、あれも一種の追い出し部屋ですね。明らかに閑職とわかるような、生産終了製品のメンテやらサポート部門なんかに集めて敗戦処理させる会社も、緩やかな追い出し部屋と言っていいでしょう。
世の中には確かに「我が社は家族経営で終身雇用です」みたいなことを宣伝する経営者もいます。そして、そういう会社に憧れる人も少なからず存在します。でも、そうした場合の“家族”というのはその企業にとって有用な人材のみを指す言葉であって、誰もがもろ手を挙げて迎え入れられるわけではありません。というわけで、そうしたパラダイス職場を夢見る時間があったら真面目に勉強してスキルアップした方がいいというのが、筆者からがっついたビジネスパーソンへのアドバイスですね。
以降、
“採用試験有料化”からも見えてくる同社のジレンマ
オーナー経営者が終身雇用好きな本当の理由
※詳細はメルマガにて(夜間飛行・BLOGOS・ビジスパ)
Q:「同僚の東大OBがものすごく仕事が出来なくて驚いています」
→A:「人はいったん気持ちが後ろ向きになると並大抵のことではリカバリーできません」
Q:「大学入学まで恋愛御法度という教育法についてどう思いますか?」
→A:「禁止されてないけど恋愛とは無縁だった東大男子を大勢知ってるのでどっちでもいいです」
ショートショート 「おれがあいつであいつがおれで 平成安保編」
Q&Aも受付中、登録は以下から。
・夜間飛行(金曜配信予定)
・BLOGOS(金曜配信予定)
・ビジスパ(木曜配信予定)
ドワンゴの川上会長といえば、以前から熱心な終身雇用論者としても有名ですね。
新卒を「じっくりと育てる」のは、終身雇用だからこそできることです。必要なときに雇い、不要になったら解雇できると都合がいいですが、これが通用するのは、日本では限られた業界や職種だと思います。
なんてセリフを見ると、なんだか連合や重厚長大メーカーの役員の話を聞いてるような気分になります。
さて、そんな異色のドワンゴですが、OBのブログでしっかり「追い出し部屋」があることが明らかとなり、一部で話題となっています。
参照:ドワンゴは大量退職に関する印象操作をやめろ
しかも、総務に集めて社内の備品補充させるって相当えげつないですね。普通の大企業なら温情措置として元の部署や事業所から隔離します。まあ悪く言えば横のつながりを絶つという意味もありますが、元の同僚と顔を合わせなくてもすむようにとのささやかな気遣いも入っています。それを社内の備品補充して回らせるって、なんだか毎日、市中引き回しするようなもんですね。ようやるわと思います。
なぜ「新人をじっくり育てたい」会社が人を追い出す必要があるんでしょうか。というか、そもそも会長の言う“終身雇用”とは何なのでしょうか。いい機会なのでまとめておきましょう。
なぜトップは終身雇用を美化し、人事部は否定するのか
実は、終身雇用の方がいいと考えている経営トップは意外と多くて、ざっくり筆者の感覚で言うとだいたい3割くらいはそうですね。これは恨まれるのがイヤだとか世間体云々ではなく、本気で「終身雇用の方がいろいろ便利だし優れている」と信じている割合です。当然、川上氏もその一人でしょう。
一方、これが人事部長だと、恐らく9割以上は「もう終身雇用じゃやっていけない」と考えています。筆者の知る限り、例外は新日鉄くらいですね。それくらい、管理部門的には終身雇用は過去の遺物扱いとなっています。
なぜこのギャップは生まれるのか。理由はシンプルで、普段向き合っている人材が違うからです。経営トップになれば、当然、周囲には社内でも超優秀な人材が集います。そして、ことあるごとに、痒い所に手が届くような感じでサポートしてくれます。しかも彼らは忠誠心に富みいちいち年俸交渉なんかしなくてもずっと会社のために働いてくれます。終身雇用の枠内で勝ち取ったモノを今さら投げ打って飛び出したりなんて、普通のサラリーマンはしませんから。どんな無理難題を吹っ掛けても愛社精神の名のもと、過労死するまで頑張ってくれることでしょう。
一方、これが人事部だと付き合う人間は180度変わります。もちろん優秀者も相手しますけど、割合で言えば優秀者と真逆な人たちとのお付き合いが圧倒的になります。具体的にはこんな人たちです。
・最低限、言われたことしかやらない人
・言われたことすらやらずに、ただ席に座ってるだけのマネキン状態の人
・仕事はしないけど休み時間にマルチの勧誘する人
・仕事はしないけど休み時間に宗教(ry
・たいして仕事してないクセに残業時間だけは毎月きっちり100時間付ける人
・めんどくさい仕事がたまるとばっくれる人
・有休に加えてよくわからない理由でさらに何か月か休む人
・病気休職から復職して数か月後にまた休職しようとする人
・上司や同僚に監視されいじめられていると言い張る人
・なんでパソコン使わないんですか?と内線で尋ねると「FBIに盗聴されているからです」と手紙持ってくる人
・異動先が気に入らないという理由でサボタージュする人
・上司に注意されると暴れる人
・懲戒解雇されたのになぜか毎日会社に来て居座る人
・社外ユニオンと組んで会社から金引っ張ろうとする人
上記のようなステキな方々との終わりの無い死闘を繰り広げるのが勤労部門のメインの仕事だったりします。よく、現場知らない労働弁護士とか実質社会経験ゼロの学者あたりが「日本企業もやろうと思えば解雇は出来る」って言ってたりしますけど、あれ嘘ですから。たとえば何にもやろうとしないマネキンを解雇するなら、業務命令書を毎日作って本人に手渡して、なにもやらなかったという証拠をそれなりの期間(たとえば一年くらい)積み重ねた上で解雇したら裁判になっても多分勝てるんでしょうけど、ただでさえ本業で忙しいのにそんなめんどくさいことやってる人事の人に会ったことないですね。
というわけで人事の人間ならたいていは終身雇用という仕組みそのものに厭世的になっているものです。まとめると、組織内できわめて優秀で忠実な人材に囲まれているがゆえにトップは終身雇用を愛し、超問題児と日々顔を突き合わせている管理部門はその限界を痛感しているというわけです。
という観点からすれば、川上氏の「社員を部品みたいに使い捨てにするのは間違いだ、今の社員にはずっとうちで働いて欲しい」という意見は、飾らない本音でしょう。ただし、氏の言う“社員”なるものは、優秀でしっかり会社に貢献してくれる社員という意味であり、そうでない人は管理部門がしっかり仕事してちゃんと組織として新陳代謝させてまっせという話ですね。
そもそも、筆者は、終身雇用がちゃんと維持されている組織で、“追い出し部屋”的な要素がまったく存在しない組織はありえないと思っています。どんな組織であれ、雇用調整の要は必ず生じます。であれば、人を解雇できない以上、追い込んで自発的に辞めさせるための仕組みが必ず必要だからです。たとえば、霞が関のキャリア官僚は40歳あたりからどんどん外の組織に出されますが、あれも一種の追い出し部屋ですね。明らかに閑職とわかるような、生産終了製品のメンテやらサポート部門なんかに集めて敗戦処理させる会社も、緩やかな追い出し部屋と言っていいでしょう。
世の中には確かに「我が社は家族経営で終身雇用です」みたいなことを宣伝する経営者もいます。そして、そういう会社に憧れる人も少なからず存在します。でも、そうした場合の“家族”というのはその企業にとって有用な人材のみを指す言葉であって、誰もがもろ手を挙げて迎え入れられるわけではありません。というわけで、そうしたパラダイス職場を夢見る時間があったら真面目に勉強してスキルアップした方がいいというのが、筆者からがっついたビジネスパーソンへのアドバイスですね。
以降、
“採用試験有料化”からも見えてくる同社のジレンマ
オーナー経営者が終身雇用好きな本当の理由
※詳細はメルマガにて(夜間飛行・BLOGOS・ビジスパ)
Q:「同僚の東大OBがものすごく仕事が出来なくて驚いています」
→A:「人はいったん気持ちが後ろ向きになると並大抵のことではリカバリーできません」
Q:「大学入学まで恋愛御法度という教育法についてどう思いますか?」
→A:「禁止されてないけど恋愛とは無縁だった東大男子を大勢知ってるのでどっちでもいいです」
ショートショート 「おれがあいつであいつがおれで 平成安保編」
Q&Aも受付中、登録は以下から。
・夜間飛行(金曜配信予定)
・BLOGOS(金曜配信予定)
・ビジスパ(木曜配信予定)
スポンサーリンク