アベノミクスは正しい。
だから、その実現のため、政府は日銀人事をアベノミクスに理解のある人間で
固め「大胆な金融緩和」を実施すべきだ。
そうすれば日本は2年以内にデフレ脱却でき、日本経済は再生できる。
なんなら私が日銀総裁をやってもいい。
「大胆な金融緩和」をやると国債の金利負担が急増し、国債価格の下落で
銀行がバタバタ倒産する。
だから安倍政権は大した金融緩和なんてやる気がない。
そもそも無制限の金融緩和も現実には不可能だ。
アベノミクスは参院選までの政治的パフォーマンスにすぎない。
この2つの文章を同じ人物が書いたと聞けば、みんな驚くのではないか。
その男の名は森永卓郎センセイである。
ちなみにオリジナル文章はともに朝日新聞社のweb論座で、一か月スパン
で寄稿されている。せめて媒体変えろよとか、もうちょっと間をおけよとか
野暮なツッコミはやめよう。
きっと、モリタクなりに方針変更せねばならない“大人の事情”があったのだろう。
というわけで、彼の“大人の事情”を推測してみよう。
まず、最初のオリジナル文。
「不況の原因はデフレであり、日銀はそれを正すパワーを秘めている」
という内容で、いわゆるリフレ派の典型的なスタンスだ。
ここではそれ自体をどうこう言うつもりはない。
ただ、以前も述べたように、著者はどうも腹の底からそれを信じているわけでは
ないようで、最近はいろいろと軌道修正を図っている。
にも関わらず、なぜ今回は断言したのか。
たぶん、そんなもん絶対に実現するかよとふんでいたのだろう。
世の中には「自分は痛い思いはしたくないけど、誰かにもっと豊かにしてほしい」
と願う他力本願な人間がいっぱいいて、そういう人が喜ぶような処方箋を示して
小銭を巻き上げることをビジネスモデルにする一群のセンセイがたがいる。
何を隠そう、モリタクはそのパイオニア的存在である。だから氏としては、どうせ
実現しないだろうから、庶民の耳に響くような派手な処方箋をぶち上げたのだろう。
「自分が総裁になってもいい」と付けくわえて、他の候補者とさりげなく同格アピール
するテクなどは、さすがとしか言いようがない。
だが、幸か不幸か、彼の書いた処方箋に近い方向で、日銀人事は実現してしまった。
普通に考えれば、100点満点ではないにせよ、それはそれで評価すればいいはず。
その上で(結果が不安なら)あいつは財務省上がりだから気合いが足りない、
俺ならもっと上手くやれるはずとかなんとか、予防線を張っておけば済む話。
だが、彼は自らが書いた処方箋を破り捨ててみせた。
国債の金利負担が急増するとか銀行がバタバタ倒産するとか、そもそも無制限の
金融緩和なんて実現不可能だとまで認めてしまう。
やっぱり、彼自身はそれをまったく信じちゃいないのだ。
予防線を張ったところで、もうこの方向で大衆を引っ張るのは限界だろうと踏んだのだろう。
普通の識者なら、自らが書いた処方箋に固執し、先鋭化することで社会との接点を
失っていく。そういう“孤立した識者”はネットでいくらでも見ることが出来る。
でも、終わりが見えた以上、彼が自説にこだわることはない。
「リフレ政策の終わりの始まり」というサブタイトルは、きっとそういう深い意味なのだろう。
アベノミクスへの追い風に乗ろうという電波芸人が多い中、淡々と逆張りしてみせる
モリタクに、筆者は電波芸人としての凄みを見たように思う。
※2014年7月10日追記。
週刊誌でモリタク氏が「これから物価上昇が本格化するので景気はさらに落ち込む」と明言、従来の「インフレにすれば景気回復、私を日銀総裁にしてくれればすぐにでも実現して見せる」というスタンスから見事な寝返りをみせてくれている。
思うに、モリタク的にはメディアに出るために、単に庶民が喜びそうな「楽して豊かになれる政策」としてリフレを主張していただけで、いざやってみたら当の庶民がひーこら言い出したから慌てて寝返ったというところだろう。
というわけで、備忘録代わりにメモしておこう。
※20150331追記
モリタク氏いわく「日銀が追加緩和を見送り物価上昇を抑えるため実質賃金は上昇、日本経済の先行きは明るい」とご発言。
だから、その実現のため、政府は日銀人事をアベノミクスに理解のある人間で
固め「大胆な金融緩和」を実施すべきだ。
そうすれば日本は2年以内にデフレ脱却でき、日本経済は再生できる。
なんなら私が日銀総裁をやってもいい。
「大胆な金融緩和」をやると国債の金利負担が急増し、国債価格の下落で
銀行がバタバタ倒産する。
だから安倍政権は大した金融緩和なんてやる気がない。
そもそも無制限の金融緩和も現実には不可能だ。
アベノミクスは参院選までの政治的パフォーマンスにすぎない。
この2つの文章を同じ人物が書いたと聞けば、みんな驚くのではないか。
その男の名は森永卓郎センセイである。
ちなみにオリジナル文章はともに朝日新聞社のweb論座で、一か月スパン
で寄稿されている。せめて媒体変えろよとか、もうちょっと間をおけよとか
野暮なツッコミはやめよう。
きっと、モリタクなりに方針変更せねばならない“大人の事情”があったのだろう。
というわけで、彼の“大人の事情”を推測してみよう。
まず、最初のオリジナル文。
「不況の原因はデフレであり、日銀はそれを正すパワーを秘めている」
という内容で、いわゆるリフレ派の典型的なスタンスだ。
ここではそれ自体をどうこう言うつもりはない。
ただ、以前も述べたように、著者はどうも腹の底からそれを信じているわけでは
ないようで、最近はいろいろと軌道修正を図っている。
にも関わらず、なぜ今回は断言したのか。
たぶん、そんなもん絶対に実現するかよとふんでいたのだろう。
世の中には「自分は痛い思いはしたくないけど、誰かにもっと豊かにしてほしい」
と願う他力本願な人間がいっぱいいて、そういう人が喜ぶような処方箋を示して
小銭を巻き上げることをビジネスモデルにする一群のセンセイがたがいる。
何を隠そう、モリタクはそのパイオニア的存在である。だから氏としては、どうせ
実現しないだろうから、庶民の耳に響くような派手な処方箋をぶち上げたのだろう。
「自分が総裁になってもいい」と付けくわえて、他の候補者とさりげなく同格アピール
するテクなどは、さすがとしか言いようがない。
だが、幸か不幸か、彼の書いた処方箋に近い方向で、日銀人事は実現してしまった。
普通に考えれば、100点満点ではないにせよ、それはそれで評価すればいいはず。
その上で(結果が不安なら)あいつは財務省上がりだから気合いが足りない、
俺ならもっと上手くやれるはずとかなんとか、予防線を張っておけば済む話。
だが、彼は自らが書いた処方箋を破り捨ててみせた。
国債の金利負担が急増するとか銀行がバタバタ倒産するとか、そもそも無制限の
金融緩和なんて実現不可能だとまで認めてしまう。
やっぱり、彼自身はそれをまったく信じちゃいないのだ。
予防線を張ったところで、もうこの方向で大衆を引っ張るのは限界だろうと踏んだのだろう。
普通の識者なら、自らが書いた処方箋に固執し、先鋭化することで社会との接点を
失っていく。そういう“孤立した識者”はネットでいくらでも見ることが出来る。
でも、終わりが見えた以上、彼が自説にこだわることはない。
「リフレ政策の終わりの始まり」というサブタイトルは、きっとそういう深い意味なのだろう。
アベノミクスへの追い風に乗ろうという電波芸人が多い中、淡々と逆張りしてみせる
モリタクに、筆者は電波芸人としての凄みを見たように思う。
※2014年7月10日追記。
週刊誌でモリタク氏が「これから物価上昇が本格化するので景気はさらに落ち込む」と明言、従来の「インフレにすれば景気回復、私を日銀総裁にしてくれればすぐにでも実現して見せる」というスタンスから見事な寝返りをみせてくれている。
思うに、モリタク的にはメディアに出るために、単に庶民が喜びそうな「楽して豊かになれる政策」としてリフレを主張していただけで、いざやってみたら当の庶民がひーこら言い出したから慌てて寝返ったというところだろう。
というわけで、備忘録代わりにメモしておこう。
4月の消費税率引き上げで落ち込んだ日本の景気は、今後どうなるか。政府、日銀、御用学者らは、増税による落ち込みは駆け込み需要の反動に過ぎないと口を揃え、「夏から景気は急激に回復軌道に乗る」と声高に叫んでいます。
実際、政府は無理矢理にでもそれを実現させようと画策しています。たとえば、各部署に指示を飛ばして、予算の前倒し執行を行なおうとしている。公共事業などの効果の大きい予算については、9月までの今年度前半にその6割を執行し、昨年度の補正予算に関しては、年度前半に9割を執行するよう、お達しを出しているのです。
また、政府は児童手当受給者には子供1人当たり1万円の「子育て世帯臨時特例給付金」の給付を決めましたが、その実際の支給は7~9月に行なわれる見通しです。つまり、政府は金をばらまいてでも、何が何でも7~9月期に景気を上げようとしているのです。
そうした政策による要因もあって、シンクタンクやエコノミストたちの大多数も、7~9月期から景気は戻ると見ているようです。しかし、私はそうはならない、年内いっぱい落ち続けると見ています。
なぜかというと、まず、物価上昇の本番はこれからやってくるからです。たとえば、一般家庭に一番影響の大きい電気料金は、4月からではなく5月から値上げされました。上げ幅が最大の東京電力では、消費税アップ分と輸入価格が上がった燃料費調整分、再生可能エネルギー負担金を合わせて、「平均的な家庭」の料金が4月より約5%、430円上がり8541円となります。燃料調整分は6月も上がるので、6月の電気料金はさらに上がります。その影響は各方面に及び、たとえば東京都の半分ぐらいの自治体では給食費が値上がりします。
こうした公共料金をはじめとする物価上昇は、今後もズルズルと続いていきます。その一方で、今年の春闘でもサラリーマンの賃金はほとんど上がらなかった。平均0.5%程度でした。まだ気づいている人は少ないようですが、年金も4月から受給額が0.7%カットされています。というのも、年金は2か月分をまとめて偶数月の15日に支給されるルールなので、今年の4~5月分が支払われる6月まで、多くの年金生活者はカットされたことに気づかない。彼らが年金カットに気づいたとき、財布の紐を締めようと考えるのは明らかです。
物価が上がって、給料は横ばい、年金は減額で、消費行動が活性化するとは考えられません。私は、夏以降も景気は悪化し続けるとしか思えないのです。
※マネーポスト2014年夏号
※20150331追記
モリタク氏いわく「日銀が追加緩和を見送り物価上昇を抑えるため実質賃金は上昇、日本経済の先行きは明るい」とご発言。
アベノミクスがスタートして以降、日銀の金融政策は一貫して「2%の物価上昇」を目標としていた。しかし、今年に入ってから黒田東彦総裁は、その方針を転換するかのような発言をしている。これは日本経済にどんな影響を与えるのか、経済アナリストの森永卓郎氏が解説する。
* * *
日銀の黒田東彦総裁は、今年の年頭まで一貫して、「どんなことがあっても2%の物価上昇目標は変えない。あらゆる手段を講じて2%に持っていく」と、2015年度中の達成を断言していました。
ところが、1月21日の金融政策決定会合後の記者会見で黒田総裁は、2015年度の物価見通しを2014年10月時点の1.7%から1%に下方修正。さらに、2013年4月の異次元金融緩和の開始から「2年以内に2%実現」についても「2015年度中にとは言っていない」と語り、方針の大転換を行ないました。
この舌の根も乾かぬうちの前言撤回により、私は2015年度の日本経済は一気に光が差してきたと考えています。
いま、原油価格が大幅に下落している。この半年でほぼ半額にまで下がっています。日本は原油のほぼ全量を輸入しているので、原油価格の下落は日本経済にとっては明らかにプラスです。ただし、日本の物価を押し下げます。
その影響はすでに現われていて、生鮮食料品を除く消費者物価指数の対前年同月比の伸び率は昨年のピーク時、5月の3.4%から12月には2.5%まで着実に下がってきているのです。しかも、消費増税の影響が一巡する4月以降、消費者物価指数の対前年比上昇率は大きく下がり、限りなくゼロに近づくと見ています。
そんな状況下で、日銀が2015年度中に2%目標を死守しようとすれば、第3次、第4次の異次元緩和に踏み出さざるを得ず、その結果として1ドル=150円程度の大幅な円安になるなど、日本経済が悲惨な事態を迎えるシナリオまで考えられました。だが、黒田・日銀の方針転換により、そうした危惧は払拭されそうです。
私は2015年度の消費者物価上昇率はほぼ0%だと考えています。その一方で、賃金の伸び率はどうか。連合が決めた2015年春闘のベースアップ要求基準は「2%以上」です。安倍晋三総理が賃上げしろと大号令をかけ、経団連もそれを容認するといっているので、連合要求の半分は取れると見ます。つまり、プラス1%の賃上げになる。
物価上昇率が0%で賃金が1%上がるとなれば、実質賃金は1%アップすることになる。そのため、2015年度の日本経済は明るくなると考えているのです。
※マネーポスト2015年春号
スポンサーリンク
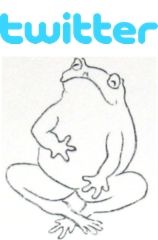









どっちかって言うと、口だけ野郎!!って思っていましたが
彼なりの計算があるんですね。