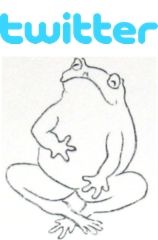今週のメルマガ前半部の紹介です。
年末の慌ただしい時期に、朝生に出演した立憲民主党の小川議員が「消費税は最低25%は必要だ」と発言し、大きな話題となりました。
まあ昔から言ってましたけどね。
【参考リンク】50年までに消費税率25%に 民主小川氏(2011.10.11発言)
ちなみに↑の50年という時期ですが、コロナでメチャクチャ大盤振る舞いしたので前倒しで30年くらいにはなってると思ってください。
さて、本発言ですけど、右はもちろん左からもバッシングされて年越し炎上しています。
でも、結論から言えば、氏の「消費税は最低25%は必要」発言は100%正しいです。特に現役世代、わけてもサラリーマンはしっかりとその真意を理解する必要があるはず。
というわけで、今回はこの消費税発言の意味するところを解説してみたいと思います。
社会保障制度が破綻して困るのは誰か
まあ予想通り右からも左からも小川氏はバッシングされているわけですが、確かにこういう人達にとっては、氏の発言は面白くないんだろうなという気はします。
・「今だけ金だけ自分だけ」と考えている人
・社会保険料をほとんど負担していない人
たとえば自分の生きてる間だけ楽をしたいと割り切ってしまった高齢者にとっては、制度や社会の持続可能性なんてどうでもいいわけです。
また、自分の両親の手厚い社会保障はどこかの太っ腹な誰かさん(=サラリーマン)ががっつり支えてくれてる↓みたいな人からすると、今の日本は文字通り“楽園”なわけです。
【参考リンク】月収300万円超の人気ふわっち配信者 臨時特別給付金の封筒から脱税疑惑が浮上
そういう人達にとっても消費税からは逃げようがないわけですから「せっかく人が気分よく生きているのにいらんこと言うな!」と怒るのも当然かもしれませんね。
そういう意味では、高齢者をメインの支持基盤とする共産党や、消費税くらいしか払って無さそうな人を支持基盤とするれいわが、この「消費税最低25%必要問題」を全力でスルーするのは当然でしょう。
社会保障年132兆円を無視してたった6兆円ぽっちの防衛費増で大騒ぎしてみせたり、「税は財源ではない」なんて珍論をぶつのも、論点をずらすという点では合理的なのかもしれません。
でも、このまま本丸の議論を避けてズルズルいくと、たぶん遠くない将来に現行の社会保障制度は維持不可能になってパンクするはずです。
英国のように野放図な財政運営に市場が鉄槌を下すか、あるいは「自分の老後資金は自分で貯蓄した方が安上がりだ」という事実に気づいた比較的余裕のある中間層が社会保障制度から流出(筆者はこっちの方がありそうと見てますが)するか。
いずれにせよ社会保障給付が190兆円を超えるとされる40年までには、社会保障制度は維持不可能になるのはほぼ確実でしょう。
【参考リンク】社会保障給付68兆円増 2040年度、政府推計190兆円
で、ここからが本題なんですが、その時にみんなはどういうリアクションするんですかね?
「今さえよければいい」という人はもちろん問題ないでしょう。無事逃げ切れた、満ち足りた人生だったと大往生してる人も少なくないはず。
社会保険料ほとんど払って無かった人は、別に嘆く理由も無いでしょう。むしろ今まで自分や親の手厚い社会保障を支えてくれた制度に感謝しつつ、これからは自分のお金でそれらを賄うことにシフトするでしょう(これまで社会保険料を負担してこなかったんだからそれくらいの余裕はあるはず)。
問題なのはサラリーマンなんですよ。
今まで何十年と給料の3割も天引きされ続けた挙句に「はい!もう社会保障おしまい!解散!これからは自分で何とかしてね」って言われて、はいそうですか、って納得するんですかね?
そりゃいきなり全部ゼロとかにはならないでしょう。でもある日突然、年金5割カット、医療費は全世代一律5割負担とかになって、今まで3割掛け捨てしてきた人は納得できるのかという話です。
って言うか、そこから自力で自分や家族の老後の面倒見る余裕なんて残ってるんですかね?年収の3割を掛け捨てにしても屁でもないくらいの超高給取りか、実家が並外れて太い人以外、普通のサラリーマンは野垂れ死ぬんじゃないかと思うのは筆者だけでしょうか。
そう考えると(共産党やれいわと違って)サラリーマンを最大の支持基盤とする立憲民主党所属の議員が、この「消費税最低25%必要問題」から逃げることなく火だるまになってでも突撃するのは、むしろやって当たり前のことなんですね。
青筋立てて小川議員を叩いている人は「余計なこと言って寝た子(=サラリーマン)を起こすんじゃないよ」というのが本音なんじゃないでしょうか。
フォローしておくと、この消費税25%というラインは後述するように本当に最低限必要なレベルなので、異次元の少子化対策とかいってバラまけばあっさり上振れするでしょう。
逆に、議論の多い高齢者の延命治療などを見直せれば、もっと低く抑えられる可能性もあります。
【参考リンク】スウェーデンにはなぜ「寝たきり老人」がいないのか
小川議員の発言というのは杓子定規に消費税上げろという意味ではなく、そういう中身のある議論をそろそろ本腰入れて始めませんか、というアドバルーン的な提言なんじゃないかと筆者はみています。
「このまま社会保障制度ほっといたら最低でも消費税25%はいくよ。でどうするの?」
そんな縁起の悪い話はするな!じゃなくて、とりあえずこの事実は認めましょうよ。でどうするのか話し合いましょう。
そういう意味でも少なくともサラリーマンは今回の提言を無視すべきではないですね。
以降、
実際、負担はどこまで上がるのか
立憲民主党から消費税に前向きな発言が出るようになったワケ
※詳細はメルマガにて(夜間飛行)
Q:「リモートワークの弊害についてどういう対策が考えられますか?」
→A:「顔を合わさないとコミュニケーションが取れないというのは思い込みです」
Q:「なんで連合ってサラリーマンの権利を声高に追求しようとしないのでしょうか??」
→A:「サラリーマンなのに消費税減税!とかインボイス反対!とか言うバカが少なくないからです」
雇用ニュースの深層
Q&Aも受付中、登録は以下から。
・夜間飛行(金曜配信予定)
年末の慌ただしい時期に、朝生に出演した立憲民主党の小川議員が「消費税は最低25%は必要だ」と発言し、大きな話題となりました。
まあ昔から言ってましたけどね。
【参考リンク】50年までに消費税率25%に 民主小川氏(2011.10.11発言)
ちなみに↑の50年という時期ですが、コロナでメチャクチャ大盤振る舞いしたので前倒しで30年くらいにはなってると思ってください。
さて、本発言ですけど、右はもちろん左からもバッシングされて年越し炎上しています。
でも、結論から言えば、氏の「消費税は最低25%は必要」発言は100%正しいです。特に現役世代、わけてもサラリーマンはしっかりとその真意を理解する必要があるはず。
というわけで、今回はこの消費税発言の意味するところを解説してみたいと思います。
社会保障制度が破綻して困るのは誰か
まあ予想通り右からも左からも小川氏はバッシングされているわけですが、確かにこういう人達にとっては、氏の発言は面白くないんだろうなという気はします。
・「今だけ金だけ自分だけ」と考えている人
・社会保険料をほとんど負担していない人
たとえば自分の生きてる間だけ楽をしたいと割り切ってしまった高齢者にとっては、制度や社会の持続可能性なんてどうでもいいわけです。
また、自分の両親の手厚い社会保障はどこかの太っ腹な誰かさん(=サラリーマン)ががっつり支えてくれてる↓みたいな人からすると、今の日本は文字通り“楽園”なわけです。
【参考リンク】月収300万円超の人気ふわっち配信者 臨時特別給付金の封筒から脱税疑惑が浮上
そういう人達にとっても消費税からは逃げようがないわけですから「せっかく人が気分よく生きているのにいらんこと言うな!」と怒るのも当然かもしれませんね。
そういう意味では、高齢者をメインの支持基盤とする共産党や、消費税くらいしか払って無さそうな人を支持基盤とするれいわが、この「消費税最低25%必要問題」を全力でスルーするのは当然でしょう。
社会保障年132兆円を無視してたった6兆円ぽっちの防衛費増で大騒ぎしてみせたり、「税は財源ではない」なんて珍論をぶつのも、論点をずらすという点では合理的なのかもしれません。
でも、このまま本丸の議論を避けてズルズルいくと、たぶん遠くない将来に現行の社会保障制度は維持不可能になってパンクするはずです。
英国のように野放図な財政運営に市場が鉄槌を下すか、あるいは「自分の老後資金は自分で貯蓄した方が安上がりだ」という事実に気づいた比較的余裕のある中間層が社会保障制度から流出(筆者はこっちの方がありそうと見てますが)するか。
いずれにせよ社会保障給付が190兆円を超えるとされる40年までには、社会保障制度は維持不可能になるのはほぼ確実でしょう。
【参考リンク】社会保障給付68兆円増 2040年度、政府推計190兆円
で、ここからが本題なんですが、その時にみんなはどういうリアクションするんですかね?
「今さえよければいい」という人はもちろん問題ないでしょう。無事逃げ切れた、満ち足りた人生だったと大往生してる人も少なくないはず。
社会保険料ほとんど払って無かった人は、別に嘆く理由も無いでしょう。むしろ今まで自分や親の手厚い社会保障を支えてくれた制度に感謝しつつ、これからは自分のお金でそれらを賄うことにシフトするでしょう(これまで社会保険料を負担してこなかったんだからそれくらいの余裕はあるはず)。
問題なのはサラリーマンなんですよ。
今まで何十年と給料の3割も天引きされ続けた挙句に「はい!もう社会保障おしまい!解散!これからは自分で何とかしてね」って言われて、はいそうですか、って納得するんですかね?
そりゃいきなり全部ゼロとかにはならないでしょう。でもある日突然、年金5割カット、医療費は全世代一律5割負担とかになって、今まで3割掛け捨てしてきた人は納得できるのかという話です。
って言うか、そこから自力で自分や家族の老後の面倒見る余裕なんて残ってるんですかね?年収の3割を掛け捨てにしても屁でもないくらいの超高給取りか、実家が並外れて太い人以外、普通のサラリーマンは野垂れ死ぬんじゃないかと思うのは筆者だけでしょうか。
そう考えると(共産党やれいわと違って)サラリーマンを最大の支持基盤とする立憲民主党所属の議員が、この「消費税最低25%必要問題」から逃げることなく火だるまになってでも突撃するのは、むしろやって当たり前のことなんですね。
青筋立てて小川議員を叩いている人は「余計なこと言って寝た子(=サラリーマン)を起こすんじゃないよ」というのが本音なんじゃないでしょうか。
フォローしておくと、この消費税25%というラインは後述するように本当に最低限必要なレベルなので、異次元の少子化対策とかいってバラまけばあっさり上振れするでしょう。
逆に、議論の多い高齢者の延命治療などを見直せれば、もっと低く抑えられる可能性もあります。
【参考リンク】スウェーデンにはなぜ「寝たきり老人」がいないのか
小川議員の発言というのは杓子定規に消費税上げろという意味ではなく、そういう中身のある議論をそろそろ本腰入れて始めませんか、というアドバルーン的な提言なんじゃないかと筆者はみています。
「このまま社会保障制度ほっといたら最低でも消費税25%はいくよ。でどうするの?」
そんな縁起の悪い話はするな!じゃなくて、とりあえずこの事実は認めましょうよ。でどうするのか話し合いましょう。
そういう意味でも少なくともサラリーマンは今回の提言を無視すべきではないですね。
以降、
実際、負担はどこまで上がるのか
立憲民主党から消費税に前向きな発言が出るようになったワケ
※詳細はメルマガにて(夜間飛行)
Q:「リモートワークの弊害についてどういう対策が考えられますか?」
→A:「顔を合わさないとコミュニケーションが取れないというのは思い込みです」
Q:「なんで連合ってサラリーマンの権利を声高に追求しようとしないのでしょうか??」
→A:「サラリーマンなのに消費税減税!とかインボイス反対!とか言うバカが少なくないからです」
雇用ニュースの深層
Q&Aも受付中、登録は以下から。
・夜間飛行(金曜配信予定)