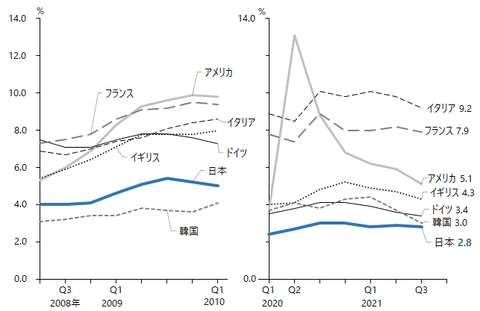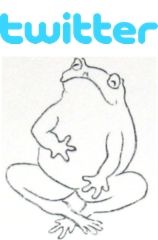今週のメルマガ前半部の紹介です。
以前からその高額な割増退職金(一説に1億5千万円とも!)で話題となっていたフジテレビの早期退職募集ですが、有名アナウンサーや往年の功労者も対象に含まれていることが判明し波紋を呼んでいます。
【参考リンク】フジ早期退職に応募したアナウンサー男女7人実名 福原直英アナの名前も
とりわけフジ競馬実況の顔的存在である福原アナの独立は競馬ファンを動揺させているようで、SMS上では「もうフジは見ない!」といった怒りの声も散見されます。
筆者自身も今回のメンツにはちょっと驚きましたね。普通、早期退職制度というのはスポットライトの当たるポジションにいる人間ほど引き止められ、出ていくのは目立たない中高年ばかりというのが相場でしたから。
恐らく、フジテレビの実施したものはそもそもリストラではなかったんだと思います。
ではフジテレビの早期退職の狙いとは何だったんでしょうか。すべてのビジネスパーソンの今後にかかわる重要なテーマですので、今回は本件について取り上げたいと思います。
早期退職には2パターン+αあり
早期退職と言えば、2000年代に電機各社とグループ企業が実施したものを思い浮かべる人が少なくないはず。事前に会社側で「辞めさせるべき人」「残すべき人」「どっちでもいい人」をセレクションした上で、面談によって誘導するというアレですね。
同じ従業員であっても「面談は終始和気あいあいとしたものだった」という人から「すごい圧迫面談されたよ」という人まで幅広く存在するので、やればやるほど組織内が疑心暗鬼に包まれるというオマケ付きです。
そうなる原因ですが、単純に経営の悪化に伴うコストカットが目的なので、企業の側に余裕が無いというのが理由ですね。
あと、このパターンだとたいてい人事部門に「全体で〇〇人辞めさせる」とか「面談で〇人誘導する」みたいな目標が課せられているので、人事の人間も顔に死相が浮かんでる人が多いですね。それくらい大変な作業なんです。
一方、数年前から大手を中心に大流行中の“黒字リストラ”は、同じ早期退職募集でもずいぶん雰囲気はライトなものです。
「中高年を減らして組織をスマートにしたい」というゆるい動機はあれど、余裕のある時期に行うものなので誘導も追い込みもありません(面談もやらない企業が多い)。むろん管理部門にノルマもありません。
早期退職募集というと、この2パターンにわかれますね。
でも、筆者は最近、もう一種類ほど早期退職の新パターンが今後出てくるのでは?と考え始めています。余裕のある黒字下で行われるので黒字リストラの亜種ではあるんですが、狙いが違うんです。
それは「従業員自身に選択肢を与え、より充実した人生を選択させる」ことなんです。
なんて書くと「そんなNPOみたいなこと考えてる企業なんてあるのか」と思う人も多いでしょうが、実は個々の従業員に常にキャリアの前向きな展望を見せておくことは、人事制度の肝なんですね。
なぜなら「将来もっと昇給するし、出世もできる」という信頼感があるからこそ、人は頑張れるわけです。もうこれ以上の上がり目が無いと思えば誰も頑張らず、『やらない理由』を探すだけになりますから。
ただ多くの日本企業では、年功序列という制度上、45歳以上の従業員にそうしたビジョンを見せることが出来なくなっています。部長ポストから役員レースへ!みたいな人も一握りはいますけど、ほとんどの人は部長職手前で打ち止めですしね。
でも、きっと誰の頭の中にも、何かしらの明るい展望は存在しているはずなんです。
故郷にUターン就職して街おこしに尽力したい、就活の時には不況であきらめた業界に今こそ再挑戦してみたい……etc
筆者はそれを、よく“ストーリー”という言い方で表現しています。
むろん、これまで培ったスキルや人脈をベースに、独立してさらなる高みを目指すのもアリです。でもまったく異分野での挑戦ストーリーを思い描けている人もいるでしょう。
【参考リンク】日本テレビの桝太一アナ、3月末で退社し大学研究員に転身
ここで重要なのは、そうした“ストーリー”はあくまで本人しか把握していないということですね。会社にできるのは「十分な退職金を用意して、そうしたストーリーのある従業員にそれを実現させるサポートをすること」なんです。
ちなみに、早期退職に伴う割増退職金には、65歳まで雇用を保証するために会社がこれまで貯め込んできたお金という意味もあります。
それを退職金に上乗せて支払うので、やりたいことがある人は自由に挑戦してくださいね、というのは、筆者にはリストラというよりも、個人の尊厳に最大限配慮した施策のように感じられますね。
逆に、会社都合で健康寿命ギリギリの70歳くらいまで薄給で引っ張りまわすような働かせ方をする会社や、そういうのがいいっていう労組って、人の人生を何だと思ってるんですかね。筆者には人間性を全否定してるようにしか見えませんけど(苦笑)
そうそう、件の福原氏は既に次のストーリーに向けて新たな一歩を踏み出しつつあるようです。競馬ファンもとりあえずは今後を見守ってみてはどうでしょうか。
【参考リンク】フジテレビ・福原直英アナ独立~武豊事務所と業務提携へ
以降、
皆で同じ夢を見ることが難しくなった日本企業
40代以降に「自分のストーリー」を実現することが日本人のゴールとなりつつある
※詳細はメルマガにて(夜間飛行)
Q: 「グループの賃下げは中途採用面接でオファーされた年俸にも適用されるか?」
→A:「もし影響あるとしても事前に教えてくれるでしょう」
Q: 「管理職昇進を断るとどれくらいマズいですかね?」
→A:「最近はそこまで気にしなくてもいいと思いますが、あえて言うなら……」
雇用ニュースの深層
Q&Aも受付中、登録は以下から。
・夜間飛行(金曜配信予定)
以前からその高額な割増退職金(一説に1億5千万円とも!)で話題となっていたフジテレビの早期退職募集ですが、有名アナウンサーや往年の功労者も対象に含まれていることが判明し波紋を呼んでいます。
【参考リンク】フジ早期退職に応募したアナウンサー男女7人実名 福原直英アナの名前も
とりわけフジ競馬実況の顔的存在である福原アナの独立は競馬ファンを動揺させているようで、SMS上では「もうフジは見ない!」といった怒りの声も散見されます。
筆者自身も今回のメンツにはちょっと驚きましたね。普通、早期退職制度というのはスポットライトの当たるポジションにいる人間ほど引き止められ、出ていくのは目立たない中高年ばかりというのが相場でしたから。
恐らく、フジテレビの実施したものはそもそもリストラではなかったんだと思います。
ではフジテレビの早期退職の狙いとは何だったんでしょうか。すべてのビジネスパーソンの今後にかかわる重要なテーマですので、今回は本件について取り上げたいと思います。
早期退職には2パターン+αあり
早期退職と言えば、2000年代に電機各社とグループ企業が実施したものを思い浮かべる人が少なくないはず。事前に会社側で「辞めさせるべき人」「残すべき人」「どっちでもいい人」をセレクションした上で、面談によって誘導するというアレですね。
同じ従業員であっても「面談は終始和気あいあいとしたものだった」という人から「すごい圧迫面談されたよ」という人まで幅広く存在するので、やればやるほど組織内が疑心暗鬼に包まれるというオマケ付きです。
そうなる原因ですが、単純に経営の悪化に伴うコストカットが目的なので、企業の側に余裕が無いというのが理由ですね。
あと、このパターンだとたいてい人事部門に「全体で〇〇人辞めさせる」とか「面談で〇人誘導する」みたいな目標が課せられているので、人事の人間も顔に死相が浮かんでる人が多いですね。それくらい大変な作業なんです。
一方、数年前から大手を中心に大流行中の“黒字リストラ”は、同じ早期退職募集でもずいぶん雰囲気はライトなものです。
「中高年を減らして組織をスマートにしたい」というゆるい動機はあれど、余裕のある時期に行うものなので誘導も追い込みもありません(面談もやらない企業が多い)。むろん管理部門にノルマもありません。
早期退職募集というと、この2パターンにわかれますね。
でも、筆者は最近、もう一種類ほど早期退職の新パターンが今後出てくるのでは?と考え始めています。余裕のある黒字下で行われるので黒字リストラの亜種ではあるんですが、狙いが違うんです。
それは「従業員自身に選択肢を与え、より充実した人生を選択させる」ことなんです。
なんて書くと「そんなNPOみたいなこと考えてる企業なんてあるのか」と思う人も多いでしょうが、実は個々の従業員に常にキャリアの前向きな展望を見せておくことは、人事制度の肝なんですね。
なぜなら「将来もっと昇給するし、出世もできる」という信頼感があるからこそ、人は頑張れるわけです。もうこれ以上の上がり目が無いと思えば誰も頑張らず、『やらない理由』を探すだけになりますから。
ただ多くの日本企業では、年功序列という制度上、45歳以上の従業員にそうしたビジョンを見せることが出来なくなっています。部長ポストから役員レースへ!みたいな人も一握りはいますけど、ほとんどの人は部長職手前で打ち止めですしね。
でも、きっと誰の頭の中にも、何かしらの明るい展望は存在しているはずなんです。
故郷にUターン就職して街おこしに尽力したい、就活の時には不況であきらめた業界に今こそ再挑戦してみたい……etc
筆者はそれを、よく“ストーリー”という言い方で表現しています。
むろん、これまで培ったスキルや人脈をベースに、独立してさらなる高みを目指すのもアリです。でもまったく異分野での挑戦ストーリーを思い描けている人もいるでしょう。
【参考リンク】日本テレビの桝太一アナ、3月末で退社し大学研究員に転身
ここで重要なのは、そうした“ストーリー”はあくまで本人しか把握していないということですね。会社にできるのは「十分な退職金を用意して、そうしたストーリーのある従業員にそれを実現させるサポートをすること」なんです。
ちなみに、早期退職に伴う割増退職金には、65歳まで雇用を保証するために会社がこれまで貯め込んできたお金という意味もあります。
それを退職金に上乗せて支払うので、やりたいことがある人は自由に挑戦してくださいね、というのは、筆者にはリストラというよりも、個人の尊厳に最大限配慮した施策のように感じられますね。
逆に、会社都合で健康寿命ギリギリの70歳くらいまで薄給で引っ張りまわすような働かせ方をする会社や、そういうのがいいっていう労組って、人の人生を何だと思ってるんですかね。筆者には人間性を全否定してるようにしか見えませんけど(苦笑)
そうそう、件の福原氏は既に次のストーリーに向けて新たな一歩を踏み出しつつあるようです。競馬ファンもとりあえずは今後を見守ってみてはどうでしょうか。
【参考リンク】フジテレビ・福原直英アナ独立~武豊事務所と業務提携へ
以降、
皆で同じ夢を見ることが難しくなった日本企業
40代以降に「自分のストーリー」を実現することが日本人のゴールとなりつつある
※詳細はメルマガにて(夜間飛行)
Q: 「グループの賃下げは中途採用面接でオファーされた年俸にも適用されるか?」
→A:「もし影響あるとしても事前に教えてくれるでしょう」
Q: 「管理職昇進を断るとどれくらいマズいですかね?」
→A:「最近はそこまで気にしなくてもいいと思いますが、あえて言うなら……」
雇用ニュースの深層
Q&Aも受付中、登録は以下から。
・夜間飛行(金曜配信予定)